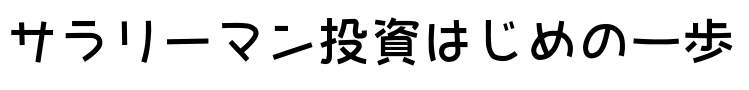将来への不安を抱えるなか、副収入や不労所得として「不動産投資」を選択する方が増えてきています。定期的に家賃収入が入ってくるため、生活にも余裕ができ、老後の心配も解消し得るため非常に魅力的。
しかし、不動産投資で家賃収入を得る際に、気をつけなければいけないのが「税金問題」。
サラリーマンなど会社勤務をしている方の場合、会社が源泉徴収の手続きをしているため、納税は自動的にされています。そのため、税金に関して、あまり良くわからないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、家賃収入にはどれくらいの税金が発生するのか、発生する税金の種類や税額などを詳しく解説します。家賃収入の税金に関する注意点や、税金対策についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。
家賃収入は「不動産所得」として税金が発生する

不動産投資により家賃収入を得た場合、家賃収入から必要経費を差し引いた「不動産所得」に対して税金が課せられます。
つまり、税金は家賃収入全体にかかるわけではなく「不動産所得」に対して発生するのです。
ここでは、混同されやすい「家賃収入」と「不動産所得」について、双方の違いを解説していきましょう。
家賃収入 = 賃貸運営で得られる売上
家賃収入とは、不動産を人に貸すことで得られる収入のこと。
借主から支払われる家賃だけでなく、礼金や敷金など、賃貸経営で発生する売上全体を指します。
家賃収入の対象となるものとして、以下が挙げられます。
- 不動産の賃料
- 敷金(借主へ返還されなかった金額が対象)
- 礼金
- 更新料
- 管理費
- 駐車場代
- アンテナ設置料金
- 自動販売機の設置による収入
不動産所得 = 家賃収入 − 必要経費
不動産所得とは、家賃収入で得られた収入から必要経費を差し引いたもの。
つまり、不動産所得とは、賃貸運営するためにかかった費用を差し引いて、実際に収入として得られた「所得」なのです。
したがって、家賃収入を得る不動産投資の場合には、「不動産所得(家賃収入−必要経費)」に対して税金が発生するということになります。
必要経費として経費計上できるのは「不動産所得という利益を得るために発生した支出」のみ。それ以外の費用は、必要経費とは認められません。
以下のような支出は、必要経費として計上できるので、覚えておきましょう。
- 物件の修繕費
- 不動産会社へ管理を委託する際の管理委託費
- ローン金利(不動産購入時のローン返済額のうち、金利に該当する金額)
- 減価償却費
- 入居者募集のための広告費
- 交際費、交通費、通信費
- 不動産取得税や固定資産税
家賃収入にかかる税金の種類と計算方法

家賃収入にかかる税金は、大きくわけて以下の3種類があります。
- 所得税
- 住民税
- 不動産を取得・保有した際にかかる税金
ここでは家賃収入にかかる税金の種類と、税金額の細かな計算方法を解説します。
所得税
上でも述べた通り、家賃収入は「不動産所得」という形で計上されます。
不動産所得は総合課税であるため、給与所得などほかの所得と合算して、課税所得を計算しなければなりません。
つまり、不動産所得以外にも給与所得や副業等による所得がある場合には、すべての所得を合算した総所得により、納税金額が決定されることになります。
不動産を保有している方が、全員一律の税金を支払うわけではないため、注意しましょう。
所得税に対する税率は、所得額が多くなるほど税率が高くなる「累進課税」です。
ここで、注意すべきは「所得税=課税所得金額×税率」ではないということ。
1,000円〜195万円までに対しては税率5%、195万円〜300万円に対しては税率10%、330万円〜695万円に対しては税率20%が課税されます。
つまり、500万円の総所得がある場合の所得税は、以下のように計算されます。
195万円 × 5% +(330万円−195万円)× 10% +(500万円 − 330万円)× 20%
= 9万7500円 + 13万5000円 + 34万円
= 57万2500円
よって、57万2,500円が所得税額となります。
ただし、上記のように計算するのはなかなか大変ですよね。
シンプルに所得税額を算出できるよう、国税庁では以下のように控除額を設定して提示してくれています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円〜195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円〜330万円以下 | 10% | 9万7,500万円 |
| 330万円〜695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円〜900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円〜1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円〜4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
(参照:国税庁「所得税の速算表」)
上記の表をもとに「課税所得金額×税率−税率控除額」で計算すれば、簡単に所得税額を算出できるようになります。
上述した例同様、500万円の総所得がある場合の計算は以下のとおり。
500万円 × 20% − 42万7500円
= 100万円 − 42万7500円
= 57万2,500円
このように簡単に計算できるため、自分の所得で計算してみてくださいね。
住民税
住民税は、定額で課税される「均等割」と、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」によって決まります。
均等割は、各自治体ごとに多少の差はあるものの、通常5,000円程度。
一方の所得割は、前年所得に対して一律10%となります。
前年の所得が500万円の場合の住民税は、以下の通りです。
均等割5,000円 + 前年所得500万円 × 税率10%
= 50万5,000円になります。
税金から控除されるものもある
所得税や住民税には、状況に応じて税負担を軽減できる各種控除があります。
と言うのも、所得税には「納税者の基本的な人権を守るために、税を負担する状況に応じた課税をする」という考えがあるから。
以下のように生きていく上で必要となる支払いは、控除対象となります。
| 種類 | 控除を受けられる場合 |
| 基礎控除 | 所得税を納税するすべての方
(38万円の控除) |
| 社会保険料控除 | 健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民健康保険料の支払い分がある |
| 医療費控除 | 一定額以上の医療費の支払いがある
(年間の自己負担医療費から、保険金と10万円を差し引いた残額が控除対象) |
| 配偶者控除 | 控除対象の配偶者がいる
(納税者の総所得金額と、配偶者の年齢に応じた控除が受けられる:おおよそ38万円の控除) |
| 扶養控除 | 控除対象扶養親族がいる
(扶養家族の年齢や同居の有無に応じた控除が受けられる:38万円〜63万円の控除) |
| 生命保険料控除 | 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料の支払いがある
(最大7万円の控除) |
| 地震保険料控除 | 地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある
(2万5,000円を最高限度額とし、それ以上の支払いに対しては控除対象) |
上記は、控除の一例にすぎません。
詳細は、国税庁のホームページ「所得から差し引かれる金額」を参照ください。
不動産を取得・保有した際にかかる税金
不動産を保有している方は、不動産を取得した初年度のみにかかる税金と、毎年払い続ける税金をそれぞれ納税しなければなりません。
初年度のみに課される税金
初年度のみに課される税金は、以下の通りです。
| 種類 | 内容 |
| 印紙税 | 不動産売買時に取り交わす「売買契約者」には、金額に応じた額の印紙の貼付が義務付けられている。 |
| 登録免許税 | 【固定資産税評価額×税率(0.5%〜2%)】
不動産を取得したことを公示するため、所有権などの権利を登記する際に課せられる。 |
| 不動産取得税 | 【固定資産税評価額×4%】
不動産を取得したときに課税される。 |
なお、印紙税は、平成26年4月1日〜令和2年3月31日の間に作成された契約書には、以下の軽減措置が適用されます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円〜50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円〜100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円〜500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円〜1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円〜5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円〜10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円〜50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
不動産を保有している間が毎年払う税金
不動産を保有している間、毎年支払わなければならない税金は以下の通りです。
| 種類 | 内容 |
| 固定資産税 | 固定資産税評価額×1.4% |
| 都市計画税 | 固定資産税評価額×0.3% |
なお、固定資産税評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、東京都や各市町村の長がひとつひとつの固定資産を評価し、算出したもののこと。
固定資産評価額は、土地や家屋の時価によって変動します。そのため、3年ごとに土地や家屋の評価の見直しが行われ、その結果に基づき固定資産評価額が決定されます。
固定資産の評価方法の詳細は、総務省のホームページ「固定資産税」をご参照ください。
家賃収入の税金で注意すべき2つのポイント

家賃収入にかかる税金は、基本的に上記で述べた所得税と住民税、不動産関連の税金のみです。しかし、なかには個人事業税や消費税が発生するケースもあるため、注意が必要になります。
家賃収入の税金で注意すべきポイントは、以下の2つ。
- 規模が大きくなると個人事業税が発生する
- 課税売上高が1,000万円以上の事業者向け賃貸経営では消費税が発生する
以下で詳しく解説します。
1、規模が大きくなると個人事業税が発生する
不動産投資等で家賃収入を得る場合、一定の規模を超えると不動産貸付業と認定され、個人事業税が課されます。
個人事業税とは、一定の事業から生じた所得が290万円を超えた場合に、その超過部分に対して発生する税金のこと。保有する不動産が多く、発生する家賃収入が多い場合、個人事業税の納税対象になる可能性があるため、注意が必要です。
認定基準の一例は以下の通り。
| 住宅用 | 一戸建て | 10棟以上保有 |
| 一戸建て以外 | 10室以上保有 | |
| 住宅用以外 | 独立家屋 | 5棟以上保有 |
| 孤立家屋以外 | 10室以上保有 |
※東京都の場合
上記に該当する場合には個人事業税として、5%の課税が発生するため注意しましょう。
2、課税売上高が1,000万円以上の事業者向け賃貸経営では消費税が発生する
家賃収入に関する税金で気をつけたいものとして、消費税の取り扱いも挙げられます。
居住用の不動産で得られる家賃収入に対しては、消費税が課されることはありません。
しかし、貸店舗や倉庫など非住居用の不動産の場合には、消費税が発生する場合も。
非課税売上高、つまり、経費を差し引く前の家賃収入が1,000万円を超える場合には、課税事業者として消費税を納める必要があるのです。
売上高が1,000万円を超えそうな場合には、消費税に注意しましょう。
なお、不動産賃貸経営において課税売上高に該当する主なものは、以下の通りです。
| 土地の賃貸
(駐車場を除く) |
建物や施設利用に伴う使用 |
| 一時的な使用・貸付期間が1ヶ月未満 | |
| 土地(駐車場) | 地面の整備をしているもの |
| フェンスや区画、建物の設置をしているもの | |
| 駐車する車両の管理をしているもの | |
| 一時的な使用・貸付期間が1ヶ月未満 | |
| 建物(居住用) | 一時的な使用・貸付期間が1ヶ月未満 |
| 建物(居住用以外) | 賃料はすべて課税売上高になる |
| 敷金、保証金、権利金など | 借主に返還されないもの |
家賃収入が発生した際に行いたい3つの税金対策

ここまでの内容を踏まえると「不動産投資で家賃収入を得ても、税金の支払いに追われそう…」と不安になる方もいるかもしれません。
でも、大丈夫です。
適切な税金対策を知っていれば、節税できます。
家賃収入が発生した際に行いたい税金対策は、以下の3つ。
- 必要経費をきちんと計上する
- 不動産所得が赤字の場合には、損益通算をする
- 青色申告をする
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
1、必要経費をきちんと計上する
家賃収入があれば、その分税金を納めなければなりません。
しかし、ここでポイントとなるのは、課税されるのは「不動産所得」つまり家賃収入から必要経費を差し引いた額ということ。
必要経費として使用した金額をきちんと計上すれば、その分税金が課される額が少なくなり、節税可能となります。
不動産経営をする上で必要となる経費はさまざまですが、計上しなかった場合でも、税務署はいちいち教えてはくれません。計上しなかった分だけ余計に税金を支払うことになってしまうため、経費は漏れなく計上するようにしましょう。
以下のような費用は必要経費として計上できるため、押さえておけると良いですね。
- 物件の修繕費
- 共益管理費
- 町内会費
- 不動産会社へ管理を委託する際の管理委託費(家賃収入代行費なども可)
- ローン金利(不動産購入時のローン返済額のうち、金利に該当する金額)
- 損害保険料(火災保険・地震保険)
- 減価償却費
- 入居者募集のための広告費
- 交際費、交通費、通信費
- 不動産取得税
- 固定資産税
なお、不動産所得の必要経費については、「不動産所得を節税する!確定申告で経費として計上できる費用とできない費用」で、詳しく解説しています。気になる方は、ぜひ一読ください。
2、不動産所得が赤字の場合には、損益通算をする
「不動産所得が赤字だったから確定申告しなくても大丈夫」という考えは、少しもったいないです。
と言うのも、不動産所得が赤字の場合に行える税金対策として「損益通算」があるから。
損益通算を行えば、不動産所得の赤字分だけ、給与所得などのほかの所得と通算することができます。
つまり、すでに給与所得から差し引かれた所得税から、赤字分の税金が返還できるのです。
確定申告をしなければ損益通算を活用できないため、赤字の場合でもしっかりと確定申告するようにしましょう。
3、青色申告をする
確定申告には、一般的な「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
青色申告では、日々の取引情報を詳細に記帳した帳簿を提出しなければなりません。
しかし、帳簿の提出と引き換えに、控除額の増額や純損失の繰越控除など、税制上の優遇を受けられるようになります。
事業規模(10室以上もしくは5棟以上)の場合は65万円の控除、事業的規模以外の場合には10万円の控除を受けられるため、節税対策に繋がるでしょう。
また、不動産所得が赤字かつ損益通算しても相殺できなかった場合、「純損失の繰越控除」を受けることもできます。
純損失の繰越控除は、翌年以降3年にわたり損失を全額繰り越せるというもの。
不動産投資の初年度は、経費がかさむことで不動産所得が赤字になることも珍しくありません。赤字分を翌年以降にも繰り越せるので、大きな節税効果にも期待できるでしょう。
青色申告は、事前の届出や詳細な帳簿、長期的な書類の保管など、手間がかかるのも確かです。しかし、税金対策として得られるメリットは大きいため、行うことをおすすめします。
家賃収入に関する税金のまとめ

不動産投資を行うことで得られる「家賃収入」は、不労所得・老後の蓄えとして非常に魅力的です。しかし、家賃収入も所得の一部であるため、所得税や住民税が必ず発生します。
自身で確定申告を行う習慣がないサラリーマンにとって、税金関連の心配や悩みは多いかもしれません。正しい知識があれば、余計な税金を支払わないだけでなく、給与所得の税金を減らすこともできます。
反対に、正しい知識がないが故に損をすることも少なくありません。
本を読んで知識を得たり、セミナーに参加したりして、正しい情報を手に入れておきましょう。不動産に関する税金のことならLINEで相談にのっていますので、お気軽に相談ください。