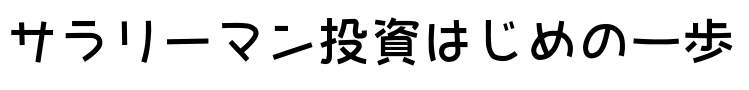不動産投資により得た利益は「不動産所得」となり、課税対象となります。
不動産投資の利益をより多く手元に残すためには、「必要経費を漏れなく計上する」ことが非常に重要。
最大の節税とも言える経費の計上ですが、どんな費用が計上できて、どういった費用は計上できないのか、正しく判断する力が必要になります。
一方、節税目的の不動産当社NGです。なぜならほとんどの不動産投資が節税になるどころか、増税になるからです。(つまり儲かっているということですが)
しかし、その増税分を可能な限り減らす術が、経費の計上です。
経費計上がうまくできなかった場合、支払う必要のない税金を納めることになったり、逆にやりすぎて脱税行為として法に触れる可能性も。
この記事では、不動産所得に関して、経費計上できる費用とできない費用について、詳しく解説していきます。不動産所得に対する税金を減らす対策も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
不動産所得とは

不動産所得とは、不動産運用で得られた金額(家賃収入)から必要経費を差し引いたもののこと。
不動産投資では、賃料や礼金、更新料、駐車場代などが「家賃収入」として得られますが、この全てが「所得」になるわけではありません。
不動産を運用をする上で発生した費用は、「経費」として家賃収入から差し引くことができるのです。
つまり、不動産所得とは「家賃収入 − 必要経費」であり、実際に収入として手元に残った所得のみが課税対象となります。
と、ここまで読むと、「給与所得と不動産所得両方ともある場合、所得税はどうなるの?」と思う方もいるかもしれませんね。
不動産所得は総合課税であるため、給与所得などほかの所得と合算して、課税所得を計算する必要があります。
所得税の計算方法や家賃収入の詳細は「家賃収入で発生する税金とは?注意点や税金対策を徹底解説」をご参照ください。
不動産所得は節税できる?

不動産投資をすれば、不労所得として家賃収入を得られます。
老後の貯蓄ができたり、生活に余裕ができたり、不動産投資がもたらすメリットは大きいでしょう。
しかし、不動産所得が増えれば、その分所得税を納めなければなりません。
「納税額が大きくならないか不安」という方もいるかもしれませんね。
ここでは、不動産所得は節税できるのかどうかを解説していきます。
【結論】不動産所得は節税できる
結論から言うと、不動産所得は節税できます。
と言うのも、上述したように、所得税は「所得」に対して課せられるものだから。
【不動産所得 = 家賃収入 − 必要経費】から算出した「不動産所得」のみにしか税金は課されません。
家賃収入が多くても、修繕費や管理費などにかかった費用が多ければ、不動産所得は少なくなり、課せられる税金も少なくなるでしょう。
ただし、確定申告で正しく漏れなく経費計上できなければ、差し引かれなかった経費も含め所得としてみなされます。その結果、多くの税金を納めることになってしまうので、注意が必要です。
このように、必要経費をきちんと計上することこそが、最大の節税と言っても過言ではありません。
不動産所得で経費計上できる10の費用

前項では「経費計上することが最大の節税」と解説しましたね。
では、実際にどういった支払いが経費にできるのでしょう?
必要経費として計上できるのは「不動産所得という利益を得るために発生した支出」のみ。
つぎの10項目以外の費用は、基本的に経費として計上できません。
- 税金
- 保険料
- 管理会社への業務委託料
- 司法書士や税理士への報酬
- 減価償却費
- 修繕費
- ローン金利
- 広告費
- 交際費・交通費・通信費
- その他
経費計上できない費用を経費として処理した場合、税務署から指摘を受けたり、追加の納税が発生することもあるため、きちんと押さえておけるといいですね。
以下でひとつずつ詳しく解説していきます。
1、税金
不動産投資を行う上で発生する各種税金は、必要経費として計上できます。
不動産投資を行う上で発生する主な税金は、以下のとおり。
| 税金の種類 | 内容 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した初年度に課せられる。
【固定資産税評価額 × 4%】 |
| 印紙税 | 不動産売買時に取り交わす「売買契約書」に貼り付ける印紙代。
売買金額に応じて400円〜60万円の課税。 |
| 登録免許税 | 不動産を取得したことを公示するため、所有権などの権利を登録する際に課せられる。
【固定資産税評価額 × 税率(0.5%〜2%)】 |
| 固定資産税 | 固定資産の所有者に課せられる税金。
【固定資産評価額 × 1.4%】 |
| 都市計画税 | 道路・下水道などの都市計画施設の整備拡充をするために、土地・家屋の所有者に課せられる税金。
【固定資産税評価額 × 0.3%】 |
このほかにも、不動産運営に使用する自動車を持っている場合には、自動車税や重量税も経費として認められます。ただし、私用での利用と併用している場合は、私用にあたらない割合のみが対象になります。
2、保険料
収益用不動産を購入する際には、火災保険や地震保険に加入するのが一般的。
とくに火災保険への加入は必須となります。
これらの保険料は、不動産を運用する上で必要不可欠な費用であるため、経費計上が可能です。
3、管理会社への業務委託料
収益用不動産を購入した場合、そのまま不動産管理会社に賃貸や建物の管理業務を委託することが一般的。
管理業務を委託すれば、トラブル対応や清掃・賃料の回収などの管理業務を一任できるため、不労所得を得やすくなります。
業務委託料の相場は、家賃の5%程度。
この5%の委託料も、不動産運営をする上で必要な費用であるため、経費計上が可能です。
4、司法書士や税理士への報酬
不動産投資を初めて行う方の場合、税金や確定申告についての相談をしたり、アドバイスをもらったりするのに、税理士と契約することも少なくありません。
また、収益用不動産を購入する際に必要な「不動産登記」の手続きを、司法書士に依頼することもあるかもしれません。
専門家へ業務を依頼する際に発生する費用も、不動産収入を得るための必要経費として計上することができます。
税理士に確定申告をお願いすれば、申告漏れの防止や税金対策のアドバイスをもらえるだけではなく、節税効果もあるのでおすすめです。
5、減価償却費
減価償却費とは、時間的経過による建物の資産価値の低下を考慮して設けられたもの。
不動産物件の建物部分は経年劣化していくため、毎年法律で定められた年数で均等に割った金額を経費計上できます。
不動産の耐用年数は、木造で22年、鉄骨造で34年、マンションに多いRC造では47年と定められています。
少し分かりにくいため、実例を見てみましょう。
| 物件 | 新築ワンルームマンション
(RC造:定額法47年、償却率0.022) |
| 購入価格 | 2,800万円
(土地建物割合;土地4:建物6) |
| 減価償却費 | 年間36.96万円ずつ減価償却 |
この場合の減価償却費は、以下の計算で求められます。
購入費用2,800万円 × 0.6(建物割合)× 償却率0.022 = 36.96万円
RC構造の法定耐用年数である47年間は、実際に出費がなくとも、毎年36.96万円を減価償却費として経費計上できるため、節税対策に役立ちますね。
なお、平成19年4月1日以降の減価償却費に関する詳細は、「国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以降に取得する場合)」を、それぞれの償却率や耐用年数は耐用年数省令別表八、耐用年数省令別表九、耐用年数省令表十を参照ください。
平成19年3月31日以前に不動産を取得した場合は、「国税庁 No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)」を参照ください。
不動産による節税は、法律で定められた耐用年数による価値の下落と、市場価値にギャップがあるため成立する節税方法になります。一時期は海外不動産で似た手法を使った節税スキームがありましたが、ここ1~2年で国税庁がNG判定したためできなくなった経緯があります。
6、修繕費
建物や部屋は、時間とともに老朽化や劣化が必ず生じます。
原状回復のための修繕費は、不動産収入を得るために必要な経費として、計上することができます。
修繕費として、経費計上できる費用として、以下のようなものが挙げられます。
- 部屋のクリーニング代
- 壁紙の交換費
- 給湯器やエアコンの交換費
- 共用部分の清掃費やメンテナンス費
- 修繕積立金
ただし、工事費用が20万円を超えるような大規模な修繕や、機能向上のための設備投資にかかった費用は修繕費に該当しません。これらは「資本的支出」となり、減価償却の対象になります。
部屋に元々なかった設備を追加する場合は、減価償却の対象になるということですね。例えば部屋に備え付けの乾燥機を新たに取り付けた場合などが該当します。一方給湯器の修理は修繕にあたるので資本的支出にはなりません。
機能向上のための費用や大規模修繕は、それぞれの設備や建物の法定耐用年数に従い、減価償却費として計上するようにしましょう。
7、ローン金利
ローンを利用して収益用不動産を購入した場合、毎月決まった額の返済が発生します。
不動産購入費用は減価償却費として毎年経費計上できますが、ローン返済時に発生する金利も、経費として計上することが認められています。
また、ローンを組んだ年に発生した手数料も、必要経費として計上可能です。
8、広告費
収益用不動産の入居者を募集するために、Web広告やチラシ等を用いることもあるでしょう。
その際に発生する広告費も、経費として計上できます。
9、交際費・交通費・通信費
交際費や、交通費、通信費も経費として計上できます。
これらの費用は、不動産収入を得るために動いたときに発生することがほとんど。
例えば、不動産会社や税理士との打ち合わせの際の飲食代や手土産代は「交際費」、購入する不動産の内見時に発生した公共交通料金やガソリン代等は「交通費」など。
また、不動産の情報を収集するために用いたインターネット使用料や、不動産会社との連絡に使用した電話料金なども「通信費」として、計上可能です。
10、その他
その他にも、不動産関連の税金に関する本を購入した際の書籍代や、不動産を保有する地域の町内会費なども、経費として計上できます。
このように、不動産収益を得るためにかかった費用は、常識の範囲内であれば、基本的に経費として計上可能です。
しかし、交際費や交通費の額や頻度があまりに多い場合には、税務署のチェックが入ることもあるため、注意しましょう。
不動産所得で経費計上できない費用

ここまで、不動産投資で経費として計上できる費用を紹介しましたが、一方で経費計上できない費用も存在します。
もちろん「経費」である以上、不動産運用に関係のないものは経費計上できません。
誤って計上してしまった場合には、税務署からの調査が入り、場合によっては「脱税行為」とみなされることも。そうならないためにも、経費として計上できない費用についても、しっかりと把握しておけると良いでしょう。
所得税・住民税
所得税や住民税は、全国民に納税義務があります。
不動産を所有していてもしていなくても支払わなければならないものであり、不動産の所有の有無は関係ありません。そのため、不動産所得の経費に含めることもできません。
不動産投資に関係ないもの
不動産投資の経費として計上できるものは、不動産所得を得るために必要となる費用のみ。
そのため、不動産運用にまったく関係のない出費は経費になりません。
不動産運用に関係のない食費や旅行の費用等は、経費として計上してはいけないため、注意しましょう。
また、打ち合わせの際に着用するスーツに関しても、経費計上できない場合も。
業務上スーツや時計、靴などが必要になることもありますが、これらはプライベートでも使用できるため、ファッションアイテムという扱いとなります。
完全に”仕事上でしか使用しない”ことの証明ができれば経費として計上できますが、そうでない場合には税務署から指摘を受ける可能性があるため、注意しましょう。
不動産所得で行いたい3つの節税対策

不動産所得を得た場合、できることなら節税したいですよね。
ここでは、不動産所得を得た場合に行いたい3つの節税対策を紹介します。
- 青色申告をする
- 不動産所得が赤字の場合は損益通算を
- 事業規模が大きい場合は法人化も検討
1、青色申告をする
確定申告をする際に「青色申告」を行うことで、節税対策に繋がります。
確定申告には、一般的な「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
青色申告を行う場合、日々の取引情報を詳細に記帳した帳簿を提出しなければなりません。やや手間に感じるかもしれませんが、帳簿の提出と引き換えに、控除額の増額や純損失の繰越控除など、税制上の優遇を受けられるというメリットも。
事業規模(10室以上もしくは5棟以上)の場合は65万円の控除、事業的規模以外の場合には10万円の控除を受けられるため、節税対策に繋がるでしょう。
また、不動産所得が赤字の場合、損益通算といって、不動産所得の赤字分だけ、給与所得などのほかの所得と通算することができます。損益通算をすれば、すでに給与所得から差し引かれた所得税から、赤字分の税金を返還できるようになります。
しかし、損益通算しても赤字が相殺できないこともしばしば。
そんな場合でも、青色申告をしていれば「純損失の繰越控除」を受けることができます。
純損失の繰越控除とは、翌年以降3年にわたり損失を全額繰り越せるというもの。
不動産投資の初年度は、修繕費や不動産取得税などの経費がかさむことで、不動産所得が赤字になることも珍しくありません。赤字分を翌年以降にも繰り越せるので、数年単位での節税効果にも期待できるでしょう。
青色申告は、事前の届出や詳細な帳簿、長期的な書類の保管など、手間がかかるため怪訝にされることも多いです。しかし、税金対策として得られるメリットは大きいため、行うことをおすすめします。
2、不動産所得が赤字の場合には、損益通算をする
不動産所得が赤字の場合には「損益通算」を行うことで、節税が可能になります。
所得税は総合課税であり、不動産所得と給与所得などほかの所得を合算した額に課されるもの。そのため、不動産所得が赤字だった場合には、給与所得等から事前に納めた税金を返還してもらえるのです。
「不動産所得が赤字だったから」と確定申告しなければ、損益通算できません。
本来であれば損益通算にて赤字分の納税義務がなくなりますが、それが受けられなくなってしまうのです。
不動産所得が赤字であった場合にも、しっかりと確定申告するようにしましょう。
3、事業規模が大きい場合は法人化も検討
複数の不動産を所有している場合、不動産所得も多くなることでしょう。
その場合、法人化を視野に入れる方も多いかもしれません。
個人としての所得にかかる所得税は「累進課税」。
そのため、不動産所得が多くなればなるほど、課される税額も多くなり、最大で45%もの税率になります。
一方で、法人税は規模や法人の種類により異なるものの、税率は一定。
不動産所得が多くなる場合には、法人化した方が納税額を低く押さえられる可能性が高いのです。
なお、個人の所得税と法人の税率の違いは、以下のとおり。
| 法人税(※普通法人の場合) | 所得税 | ||
| 課税対象 | 法人の所得
(法人の利益から経費を差し引いた額) |
個人の所得 | |
| 課税方法 | すべての所得に課税される | 所得が10種類に分類され、種類ごとに計算方法が異なる | |
| 税率 | 資本金1億円以下の中小法人 | 年間所得800万円以下の部分:15% | 超過累進税率 所得額に応じて5%〜45% |
| 年間所得800万円超の部分:23.2% | |||
| 中小法人以外の法人 | 23.2% | ||
また、法人化することで、経費として計上できる範囲も広がります。
経費計上できる範囲も広くなるため、その分課税対象額も低くなり、節税に繋がるでしょう。
経費計上できる範囲が広くなるというと漠然としているかもしれませんが、
例えば法人の定款にブログアフィリエイトなどが入っていると、それに関わる費用を経費として計上できるようになります。
ブログアフィリエイトを事業とする場合、それに必要な取材費用として、ブログで紹介するサービスの費用や商品も経費計上できる場合があります。
また、事業で関わる人たちとの交際費も経費として落ちるため、不動産に限らずあらゆる内容で経費が計上できるようになります。もちろんある程度実態が伴っていないと脱税とみなされるケースもあるので、ほどほどにではありますが。
節税目的の不動産投資はNG
ここまで、不動産投資でいかにして税金を抑えるかをお伝えしてきました。
しかし、節税目的で不動産投資をすることはNGです!冒頭でもお伝えした通り、不動産投資はほとんど増税になるため、です。
もちろん初年度は節税になりますが、その分初期費用として100万円近い支出が発生しています。
2年目以降はほとんどのケースで増税です。
もしあなたが節税目的の不動産投資営業を受けているなら、その不動産会社は良い物件が仕入れられない業者だと思ってください。
不動産所得と経費のまとめ

不動産所得は、しっかりと経費計上することで節税できます。
ただし、経費計上できる費用は「不動産所得を得るために発生した費用」のみ。※法人化すればその限りではありません。
修繕費や減価償却費、管理会社への業務委託料など、不動産運営に関する費用は経費として計上できます。一方で、住民税や所得税など、不動産経営とは関係のない費用に関しては、経費計上できません。
誤って計上してしまった場合には、脱税行為とみなされることもあるため、注意しましょう。
とは言え、初めて不動産投資を行う場合や、確定申告に不慣れな場合には、確定申告や節税対策に不安がある方も多いと思います。正しい知識がないと、多く税金を支払わなければいけなかったり、法に触れたりしてしまうリスクも。
不動産投資や節税対策などに関する相談にものっているので、気になる方はLINEで相談ください。