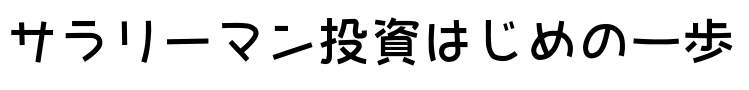不動産の所有期間が5年を超える場合「長期譲渡所得」、不動産の所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」に該当します。長期・短期では、発生する税率が大きくことなるため、損しないためには売却タイミングが非常に重要になります。この記事では、長期・短期譲渡所得の違いや節税のポイントを徹底解説します。
将来の安定した収入や節税対策として、不動産投資が注目を集めています。不動産投資で安定したマンション経営を行えれば、不労所得も夢ではなく、また、将来的に不動産を売却することでまとまったお金が手に入る可能性もあります。
しかし、不動産を売却する際には、少し気をつけなければならないことも。
不動産を売却した際には、売却して得た所得(譲渡所得)に対して、所得税や住民税といった税金が発生します。譲渡所得の存在を知らずにいると、不動産売却によりトータル収支がマイナスになってしまうリスクも…。
ここでは、不動産投資における出口戦略を考えるうえで、必ず知っておきたい「譲渡所得」に関して、長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いや税金の計算方法などを徹底解説します。
損をしないためにできる対策も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
譲渡所得とは

譲渡所得とは、不動産など所有している資産を売却した際に生じる所得のこと。
不動産を売却して得た収入金額から、その不動産の取得費と売却するときに発生した譲渡費用を差し引いた額が「譲渡所得」になりますが、譲渡所得に対して所得税や住民税が発生します。
生じた所得を譲渡税以外の所得として課税したり、所得税が発生しない譲渡所得があったりと、細かな決まりごとがあるので、注意が必要。
とくに、土地や建物といった不動産の売却においては、譲渡所得が分離課税となります。給与所得など他の所得と損益通算できないため、売却額に対してダイレクトに税金が発生します。
つまり、譲渡所得税がどれくらいかかるのか分からずに投資をしてしまうと、売却時に発生する譲渡所得税により投資で得た利益が減ってしまうことも。譲渡所得税が高額なケースでは、最悪の場合、トータル収支がマイナスになってしまう可能性があるため、きちんと把握しておけるといいですね。
なお、譲渡所得は、不動産を保有している期間により「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられます。保有期間の違いにより、税率が異なるため、以下で詳しく解説していきます。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い
不動産の所有期間が5年を超える場合「長期譲渡所得」、不動産の所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」に該当します。
この場合の「5年」とは丸5年の考えではなく、「売却した年の1月1日時点での所有期間」を指しているため、間違えないようにしましょう。
長期譲渡所得と短期譲渡所得では、以下のように、所得税や住民税の税率が大きく異なります。
| 所得税 | 住民税 | 計 | |
| 長期譲渡 | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡 | 30.63% | 9% | 39.63% |
譲渡所得税の算出方法

譲渡所得税は「譲渡所得税 = 譲渡所得金額 × 譲渡税率」で決まります。
この「譲渡税率」にあたる部分が、前述した長期譲渡所得と短期譲渡所得で大きく異なってくるというわけです。
譲渡所得金額は「収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額」で算出可能になりますが、それぞれの費用に関して、以下で詳しく解説していきます。
収入金額
収入金額とは、不動産を売却したことで買主から受け取る金額を指します。
不動産を現物出資して株式を受け取るなど、金銭以外の物や権利で受け取った場合には、該当する物や権利の「時価」が対象となります。
取得費
取得費とは、売却対象の不動産を購入した際に生じた費用を指します。購入代金だけでなく、購入時に要した仲介手数料や登記費用、購入後の改築費用も取得費に該当します。
ただし、経過年数による価値の減少があるため、経過年数に応じた減価償却費を差し引かなければなりません。(参考:建物の取得費の計算|国税庁)
また、購入から長期間経過している場合には、取得費の詳細がわからないということもあるかもしれませんよね。その場合は、売却価格の5%を取得費とすることが可能です。
(取得費が売却した不動産の5%相当額より少ない場合も、概算取得費として5%で換算可能)
さらに、相続や贈与により不動産を取得した場合には、相続・贈与の評価額ではなく、前の所有者の取得費を引き継ぐことも可能。なお、相続・贈与などの名義変更のための登記費用や更新手数料などは、取得費として加算することができます。
ただし、5%の概算取得費を適用する際には、登記費用を加えることはできないため、注意しましょう。
譲渡費用
譲渡費用とは、不動産を売却する際に支払った費用を指し、以下のものが該当します。
- 土地や建物を得るために支払った仲介手数料
- 印紙税で売主が負担したもの
- 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
- 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
- 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
- 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
(引用:譲渡費用となるもの|国税庁)
特別控除額
特別控除額とは、一定の条件を満たす場合に所得から控除できる金額のことであり、以下のものがあります。
- 収用等により土地建物を譲渡した場合:5,000万円
- マイホームを譲渡した場合:3,000万円
- 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合:2,000万円
- 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合:1,500万円
- 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合:1,000万円
- 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合:800万円
- 低未利用土地等を譲渡した場合:100万円
長期譲渡所得と短期譲渡所得の計算例

ここでは、実際に長期譲渡所得と短期譲渡取得の計算をしていきましょう。
| 【購入・売却条件】 |
| 6,000万円(土地3,000万円+建物3,000万円)で購入した築20年の木造アパートを、6,000万円で売却。
購入時にかかった費用は、登記費用200万円、仲介手数料200万円、減価償却費は3,000万円。 売却時にかかった仲介手数料は200万円、特別控除の適用はなし。 |
まずは、譲渡所得金額の計算を行います。
譲渡所得金額は、【①収入金額 −(②取得費 + ③譲渡費用)− ④特別控除額】で算出でき、それぞれの計算は以下のとおり。
| ①収入金額 | 売却額:6,000万円 | 6,000万円 |
| ②取得費 | 購入費:6,000万円
購入時に発生した登記費:200万円 仲介手数料:200万円 から、減価償却費3,000万円を差し引いた額 |
3,400万円 |
| ③譲渡費用 | 売却時の仲介手数料:200万円 | 200万円 |
| ④特別控除 | なし | 0円 |
上記を譲渡所得金額の計算式に当てはめると、以下のように算出できます。
譲渡所得金額
= 収入金額6,000万円 −(取得費3,400万円 + 譲渡費用200万円)− 特別控除額0円
= 2,400万円
譲渡所得税は、【譲渡所得金額×譲渡税率】で算出できますが、譲渡税率は長期譲渡と短期譲渡で税率が異なります。以下で、長期譲渡所得税と短期譲渡取得税の計算をしてみましょう。
長期譲渡所得の場合
長期譲渡所得の場合、譲渡税率は20.315%。これを計算式にあてはめて、計算します。
譲渡所得金額2,400万円 × 譲渡税率20.315%
= 406万円
このように、譲渡所得税金は406万円となります。
短期譲渡所得の場合
短期譲渡所得の場合、譲渡税率は39.63%。これを計算式にあてはめて、計算します。
譲渡所得金額2,400万円 × 譲渡税率39.63%
= 951万円
このように、譲渡所得税金は951万円となります。
不動産の売却で損しないためにできる対策

不動産の売却では、所得税額次第では売却により損をする可能性があります。とくに、不動産投資などの場合、売却した際の税金で、トータル収支がマイナスになることも。
ここでは、不動産の売却で損しないためにできる以下の2つの対策を解説します。
- 長期譲渡所得で処理できるタイミングで売る
- 収支のシミュレーションを行う
ひとつずつ見ていきましょう。
1、長期譲渡所得で処理できるタイミングで売る
長期譲渡所得で処理できるタイミングで売却するだけで、支払う税金は約半分になります。
長期譲渡か短期譲渡かの境目は、不動産を所有していた期間が「5年」以上かどうかです。この際注意が必要なのは、不動産を所有した日から5年ではなく、「不動産を売却した年の1月1日時点での年数」ということ。
不動産を所有してから丸5年経過していても、譲渡所得の区分では5年にならないことがあるのです。例を挙げて説明すると以下のようになります。
| 購入年月日 | 売却年月日 | 所有期間 | 1月1日時点での所有期間 | 譲渡所得の区分 |
| 2010年8月1日 | 2015年9月1日 | 5年1ヶ月 | 4年5ヶ月 | 短期 |
| 2010年8月1日 | 2016年2月1日 | 5年6ヶ月 | 5年1ヶ月 | 長期 |
このように、実際の所有期間が5年を超えていても、譲渡所得の区分では5年未満と判断されるケースがあります。
長期譲渡と短期譲渡では、税率に大きな差があるため、少しでも出費を抑えるのであれば長期譲渡所得で処理できるよう、売却タイミングを検討するのが良いでしょう。
なお、ここでいう「購入年月日」は、売買契約書などを取り交わした日や引き渡し日になることがほとんど。購入年月日を正確に把握しておかないと、短期・長期の判断がつけられず、長期譲渡で処理するつもりが短期譲渡で処理されてしまったなんてことにもなりかねません。
購入年月日や引き渡し日は、きちんと確認しておけると良いですね。
2、収支のシミュレーションを行う
不動産を売却する際には、トータル収支がどうなるのか、収支のシミュレーションを行うことが大事です。
と言うのも、売却時に発生する譲渡所得税によりトータル収支がマイナスになる可能性があるから。
購入金額と売却金額が同額の場合、利益がゼロだから税金がかからないと勘違いしている方をたまに見かけます。しかし、実際には、減価償却により建物の価値が下がっている分、譲渡所得が発生するのです。
損をしないためには、トータル収支がプラスになるよう高値で売却するか、もしくは、長期所有による特別控除を受けて節税を狙うしかありません。
ただし、高値で売却するために、相場よりも高い設定で売りに出しても売れるとは限りません。不動産会社の査定額を参考にするなど、適切な価格を設定できるといいですね。
また、特別控除を受けるために長期保有し続けるのも少し危険。不動産の価値は、経年とともに下がるため意味もなく所有し続けるのはリスクを伴います。
どのタイミングで売却すれば利益が残るのか、トータル収支のシミュレーションを行えるといいでしょう。
長期譲渡所得・短期譲渡所得のまとめ

不動産を売却した際、「譲渡所得税」が生じます。所有期間が5年以上の場合「長期譲渡所得」、5年未満の場合「短期譲渡所得」に該当しますが、双方では税率に大きな違いがあります。
発生する税金は約倍の違いがあるため、損しないためにも売却タイミングは慎重に検討するようにしましょう。